「最近、高齢の家族が食事中にむせることが増えた気がする…」そんな変化に気づいたら、少し注意が必要です。むせるという行為は誰にでも起こりうることですが、高齢の方の場合は、食べ物や飲み物をスムーズに飲み込む力「飲み込む機能」が低下している兆候かもしれません。
もし、そのままの状態が続くと、食べ物や飲み物が誤って気管に入ってしまう「誤嚥(ごえん)」を引き起こす可能性があります。さらに、誤嚥を繰り返すと、肺に細菌が入り込み、誤嚥性肺炎という重い病気につながることもあります。
この記事は、そんな不安を感じているご家族の方に向けて、以下の情報をお届けします。
- 高齢者が食事中にむせる原因とは?
- むせを防ぐために、家庭でできる予防策
- むせを放置することの危険性
- 大切な家族の健康を守るための「5つのチェックポイント」と具体的な対策
高齢者のむせは、早期に気づき、適切な対策を講じることが非常に大切です。この記事を参考に、ご家族の健康を守るための一歩を踏み出してみませんか?
なぜ高齢者のむせは危険なの?誤嚥との関係
食べ物や飲み物が誤って気管に入ると、体は反射的にむせて、異物を外へ出そうとします。しかし、高齢になると、飲み込む機能が弱まっているため、うまく飲み込めなかったり、気管に入ったものを十分に排出できなかったりすることがあります。
この誤嚥が頻繁に起こると、口の中の細菌や食べ物が肺に入り込み、誤嚥性肺炎を引き起こすリスクが高まります。特に高齢者は免疫力が低下していることが多いため、肺炎が重症化しやすく、場合によっては命に関わることもあります。
「最近、むせることが増えた」と感じたら、決して見過ごさずに、早めの対応を心がけましょう。
高齢者の誤嚥を防ぐための5つのチェックポイント

誤嚥とは、食べ物や飲み物が食道ではなく、誤って気管に入ってしまうことです。通常、食べ物を飲み込む際には、喉の筋肉が連携して働き、食べ物を食道へと運びます。しかし、この機能が衰えると、食べ物が気管に入りやすくなり、咳や窒息を引き起こすことがあります。以下の5つのポイントをチェックしてみましょう。
② 水分を飲んだ時にむせていないか?
③ 食事中の姿勢は適切か?
④ お口の中は清潔に保たれているか?
⑤食事の内容や食べ方に工夫はされているか?

日々の食事の際に、注意深く観察することが大切ですね。
チェック1:食事中にむせる回数が増えていないか?
食事中に以下のような様子が見られる場合は、注意が必要です。
☑食事中に何度も咳き込んだり、むせたりする
☑口の中に食べ物が残りやすくなった
☑ 食後に声がかすれたり、喉がゴロゴロするような音がする
これらの兆候が見られる場合は、誤嚥のリスクが高まっている可能性があります。
チェック2:水分を飲んだ時にむせていないか?
水やお茶などのサラサラした液体は、高齢者にとって特に飲み込みにくいことがあります。もしむせやすい場合は、以下のような工夫を試してみましょう。
◆ 「ゼリー状の飲料」を活用する
◆スプーンで少量ずつ、ゆっくりと飲ませる
水分摂取時のむせは、誤嚥性肺炎のリスクを高めるため、慎重な対応が必要です。
チェック3:食事中の姿勢は適切か?
食事中の姿勢が悪いと、飲み込む力が十分に発揮できなかったり、食べ物が気管に入りやすくなったりします。理想的な姿勢は以下の通りです。
♥足の裏をしっかりと床につける(膝の角度が90度になるように調整)
♥ 顎を軽く引いた姿勢を保つ(上を向いて飲み込むと誤嚥しやすくなります)

足が床につかない場合は、台などを利用して高さを調整しましょう。少し前かがみになり、顎を引いた姿勢で食事をすることが大切です。また、食事前に軽い体操を行うことも、飲み込む機能の維持に役立ちます。
チェック4:お口の中は清潔に保たれているか?
口の中が乾燥していたり、食べかすが残っていたりすると、細菌が繁殖しやすくなり、飲み込む機能にも悪影響を及ぼす可能性があります。口腔ケアのポイントは以下の通りです。
☘入れ歯を使用している場合は、毎日清潔に保つ
☘唾液の分泌を促すために、食後にガムを噛んだり、口腔マッサージを行ったりする
適切な口腔ケアは、誤嚥性肺炎のリスクを低減するために非常に重要です。
チェック5:食事の内容や食べ方に工夫はされているか?
高齢者が安全に食事をするためには、食事の内容や食べ方にも工夫が必要です。
★豆腐、卵料理、煮込み料理など、柔らかく飲み込みやすい食品を選ぶ
★一口の量を少なくし、ゆっくりと時間をかけて食べる
★食べ物をしっかりと噛んでから飲み込む(目安として30回程度)
食事中は、焦らず、リラックスした雰囲気で食事ができるような環境を整えることも大切です。
高齢者のむせを予防するためにできること
日常生活の中で、以下の点に注意することで、むせを予防し、誤嚥のリスクを減らすことができます。
嚥下体操を取り入れる
飲み込むための筋肉を鍛えることで、むせにくくなります。
・首をゆっくり回すストレッチ
・飲み込む練習(唾を何度か続けて飲む)
生活習慣を見直す
・食後30分程度は、横にならずに座った姿勢を保つ。
・適度な運動を習慣にし、全身の筋力低下を防ぐ(飲み込む機能の維持にもつながります)。
私の体験談
ショートステイ利用の高齢者の女性Aさん(87歳)は、ご家族から最近食事中によくむせるという報告を受けていました。軽度のアルツハイマー型認知症では、体の不調を訴えられない傾向があります。
昼食は施設で、ご飯は二度炊き、副菜は刻み食、汁物にはとろみを付けて提供しました。ご自身で食べられますが、様子を見ると食事が進みません。声かけ手を握ると熱感がありました。直ちに近くにいた看護師に報告し、体温を測ると37.8度あり、ご家族に報告。医療機関に受診していただきました。その結果、誤嚥性肺炎の疑いがあると診断され一時観察入院となりました。
まとめ:高齢者のむせは大切なサインです
高齢者の食事中のむせは、誤嚥性肺炎につながる可能性のある重要なサインです。今回ご紹介した5つのチェックポイントを参考に、日頃から注意深く観察し、早めの対策を心がけましょう。
- ✅ 食事中にむせる回数が増えていないか?
- ✅ 水分を飲んだ時にむせていないか?
- ✅ 適切な姿勢で食事ができているか?
- ✅ 口腔ケアはきちんと行われているか?
- ✅ 食事の内容や食べ方に工夫はされているか?
これらの点に留意することで、誤嚥を防ぎ、高齢者が安全で快適な食生活を送れるようにサポートできます。もし、むせの症状が気になる場合は、自己判断せずに、早めに医師や専門家(歯科医師、言語聴覚士など)に相談することが大切です。
ご家族皆様で協力し、日々の食事を工夫することで、大切な高齢者の健康と笑顔を守ることができます。今日からできることから、ぜひ実践してみてください。私たちは、皆さんのこれからを応援しています。
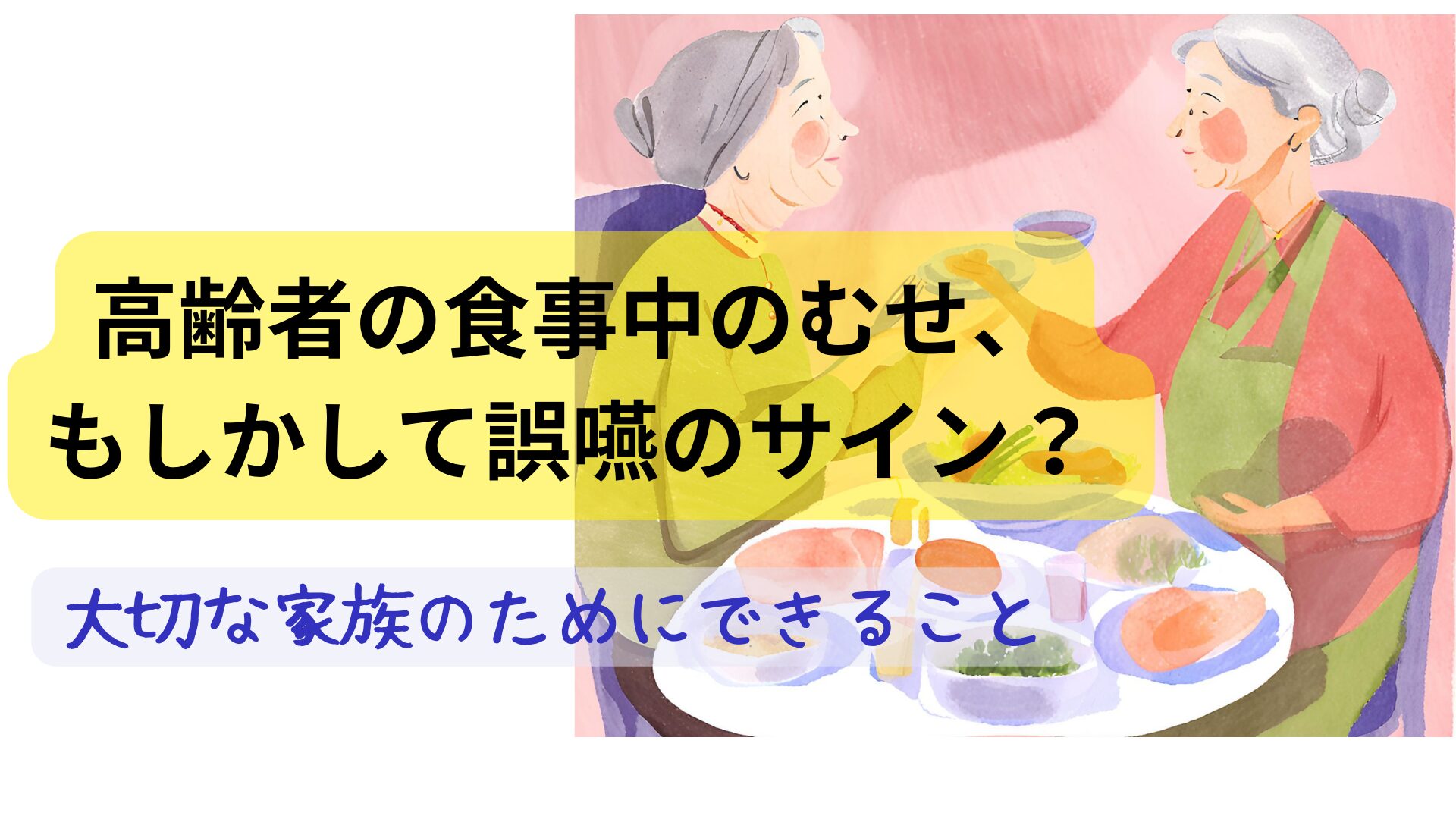


コメント