訪問介護の記録業務で、こんなお悩みを抱えていませんか?
- 「記録すべき内容が多すぎて、何から書けばいいか迷ってしまう…」
- 「どうしても抽象的な表現になってしまい、この記録で本当に伝わるのか不安…」
- 「限られた時間の中で、効率よく記録をまとめたいけれど、良い方法が見つからない…」
訪問介護の現場では、目の前の業務に追われながらも、利用者さんの状況を正確に記録することが求められます。しかし、その重要性は理解していても、実際には時間が足りず、記録が後回しになったり、内容が不十分になってしまうこともあるのではないでしょうか。
この記事を読むことで、あなたは以下の力を手に入れることができます。
- 記録の基本的なルールを理解し、どのような状況でも的確な記録ができるようになるでしょう。
- 記録作成で陥りやすいミスを事前に把握し、正確かつ簡潔な記録を残せるようになります。
- 効率的な記録方法を習得し、貴重な時間を有効活用できるようになります。
記録作成の負担が軽減されれば、より利用者さん一人ひとりに寄り添った、質の高いケアを提供できるようになるはずです。ぜひ、この記事を参考にして、日々の記録業務の悩みを解消してくださいね。
訪問介護記録作成の第一歩:その重要性を再認識しましょう
訪問介護の記録は、単なる事務作業ではありません。それは、利用者さんへのサービス提供の軌跡であり、より良いケアへと繋がる重要な情報源です。ここでは、適切な記録が求められる理由を改めて確認しましょう。
サービスの質を高めるために
日々の記録を通じて、利用者さんの状態の変化を細やかに捉え、それに応じた適切なケアを提供することができます。また、記録は、他のスタッフや次回の訪問者への大切な申し送り事項となります。さらに、介護保険サービスの報酬を請求する上でも、正確な記録は不可欠です。記録は、書いた時点で終わりではなく、定期的に見返すことで、提供している介護サービスの質を向上させるための貴重な手がかりとなるでしょう。
トラブルを未然に防ぐために
介護記録は、利用者さんやご家族との間で認識のずれが生じた際や、万が一のトラブル発生時の証拠となります。特に、身体介護の内容や、緊急時の対応については、詳細かつ正確な記録が非常に重要です。訪問介護は、利用者さんの居室というプライベートな空間で、一人でサービスを提供することが多いため、事故やトラブル発生時に客観的な状況を証明する記録は、あなた自身を守るためにも重要な役割を果たします。
法的要件と監査への対応
訪問介護サービスは、介護保険法に定められた運営基準や、行政からの指導に基づいて提供されています。記録が適切に管理されていない場合、監査の際に指摘を受ける可能性があります。日頃から正確な記録を徹底することが、法令遵守と円滑な事業運営に繋がります。
訪問介護記録を書く際の基本原則
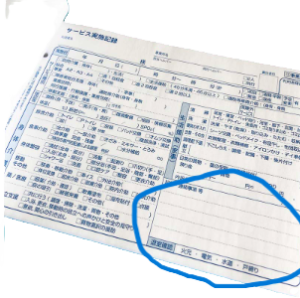
この部分に特記事項を記入
訪問介護記録の中でも、特に「特記・連絡事項」の欄は、利用者さんの状況を詳細に伝える上で非常に重要です。しかし、いざ書こうとすると、何を書けば良いか迷ってしまうこともありますよね。そこで、訪問介護記録を作成する際の基本的なルールをまとめました。これらの原則を守ることで、正確で信頼性の高い記録を作成することができます。

私の使用していたサービス提供記録簿を例に説明していきますね。
具体的に、そして簡潔に表現する
訪問介護記録は、利用者さんの状態や提供したサービス内容を、誰が読んでも明確に理解できるように記述することが重要です。記録を読む人が、まるでその場にいたかのように状況を把握できる具体性が求められます。例えば、「掃除をした」という記録だけでは、どの場所をどのように掃除したのかが伝わりません。「14時、リビングの床を掃除機で清掃。集めたゴミは指定のゴミ袋に入れ、新しいゴミ袋をセットした」のように、具体的な行動と結果を記述しましょう。また、不要な言葉を省き、箇条書きなどを活用することで、情報の整理と可読性の向上を図りましょう。
→具体的な介助内容が分からず、利用者さんの状況も不明です。良い例:「10時15分、利用者様よりトイレに行きたい旨の申し出あり。歩行状態を確認し、手すりを持ちながら安全にトイレまで移動を介助。排泄は自立されており、見守りにて完了。着衣の乱れを整え、居室まで付き添い。」
→ 時間、移動手段、介助の程度、排泄状況、その後の対応まで詳細に記録されています。
主観ではなく、客観的な事実を書く
記録は、実際に観察したことや、利用者さんから聞いた言葉を中心に記述し、あなたの感情や推測を含めないことが基本です。客観的な事実を明確に記載し、「〜だろう」「〜のように見えた」といった憶測に基づく表現は避けましょう。
良くない例:「利用者は寂しそうだった。」→ あなたの主観的な感情であり、具体的な状況が伝わりません。
良い例:「15時、利用者様は居室の窓際で一人座っており、声をかけるまで特に発言はなかった。表情は沈んでいるように見受けられた。『何かありましたか?』と尋ねると、『特にないよ』と小さな声で答えられた。」
→ 観察された事実と、利用者さんの言葉をそのまま記録することで、状況が客観的に伝わります。
良くない例:「利用者は機嫌が悪く、話しかけても無視された。」→ あなたの感情的な解釈が含まれており、具体的な状況が不明です。
良い例:「11時、利用者様に話しかけたところ、視線は合うものの返答はなかった。再度声をかけると、『今は話したくない』とはっきりとした口調で言われた。」
→ 観察された事実と利用者さんの発言を基にした記録で、状況がより具体的に伝わります。
客観的に記録するためには、「何を見たか、聞いたか」を中心に書くことを意識しましょう。
時系列に沿って記録を整理する
訪問中に起こった出来事を、発生した時間順に記録することで、利用者さんの状態の変化や、サービス提供の流れをスムーズに把握することができます。記録の順序がバラバラだと、状況の理解が難しくなります。
良くない例:「薬を渡し、掃除を行った。」
→ どちらが先に行われたのか、時間の経過が不明です。
良い例:「12時00分、利用者様に内服薬(〇〇〇mg)を手渡し、服用を確認。12時30分、リビングと寝室の掃除を実施。」
→ 時間を明記することで、行動の順序が明確になります。
良くない例:「買い物をして、着替えの介助をした。」
→ どちらのサービスが先に提供されたのかが分かりません。
良い例:「9時30分、利用者様と一緒にスーパーへ買い物に出かけ、購入品を確認後、冷蔵庫に収納。10時30分、更衣の介助を実施。新しい下着と洋服に着替えるのを見守り、一部介助を行った。」
→ 時間を追って記録することで、一連の流れが明確になります。
訪問介護の記録は、可能な限り訪問直後に作成することが理想的です。時間が経過すると、記憶が曖昧になり、正確な記録が難しくなる可能性があります。
訪問介護記録の具体的な書き方:場面別
生活援助の場合
生活援助では、利用者さんの日常生活をサポートするために行う様々な作業を記録します。具体的には、掃除、洗濯、ベッドメイキング、衣類の整理・補修、調理・配膳、買い物、薬の受け取りなどが含まれます。生活援助の記録では、「何を」「どのように」行ったかを具体的に記述します。
良くない例:「掃除と洗濯をした。」
→ どの範囲をどのように掃除し、洗濯物をどこに干したのかといった詳細が不明なため、記録としては不十分です。チェック項目だけで済ませるべき内容と判断されてしまいます。
良い例:「リビングと台所を中心に掃除機をかけ、床の拭き掃除を実施。換気扇のフィルターの汚れが目立ったため、簡易的な清掃を行った。洗濯物は、タオル類と衣類を分け、洗濯機で洗い、ベランダに干した。」
→ 作業の場所、具体的な方法、特記事項などが明確に記載されており、提供したサービスの内容が具体的に伝わります。

作業範囲や利用者の要望を明確に記録しましょう!
身体介護の場合
身体介護は、利用者さんの身体に直接触れて行う介助のことです。排泄介助、食事介助、清拭・入浴介助、身体整容、体位変換、移動・移乗介助などが主な内容です。その他、起床・就寝介助、服薬介助、自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助も身体介護に含まれます。身体介護の記録では、利用者さんの反応や介助の内容を詳細に記録します。
良くない例:「入浴を手伝った。」
→ どのように介助したのか、利用者さんの状態や反応が全く分かりません。
良い例:「入浴介助を実施。湯温は39℃で『気持ちが良い』との発言あり。ご自身で洗える部分は見守り、洗いにくい背中と足は介助を行った。湯船への出入りの際は、転倒防止のため声かけと付き添いを徹底。入浴後、皮膚の状態に異常は見られなかった。」
→ 介助の詳細な手順、利用者さんの発言、安全への配慮、入浴後の状態などが具体的に記録されています。

介助の範囲や利用者の反応を詳しく記録しましょう。
状態変化があった場合
利用者さんの体調や精神面に変化が見られた場合は、観察した事実と、それに対して行った対応を時系列に沿って記録します。
例:「15時00分、利用者様より『胸が締め付けられるような感じがする』との訴えあり。顔面蒼白で、呼吸も浅い様子が見られたため、バイタルサインを測定。血圧90/60mmHg、脈拍110回/分。SpO2 92%。すぐに家族に電話連絡し、状況を説明。救急車の手配について指示を仰ぎ、救急隊員到着まで付き添い、状況説明を行った。」
→ 状態変化の発生時間、具体的な症状、測定したバイタルサイン、家族への連絡状況、その後の対応などが時間経過とともに記録されています。
訪問介護記録でよくあるミスと改善策
あいまいな表現の使用
訪問介護記録でよく見られるのが、具体性に欠けるあいまいな表現です。このような記録は、監査時や他のスタッフへの情報伝達において、誤解や混乱を招く可能性があります。
改善前:「昼食の準備を手伝った。」
→ どのような準備を、どの程度手伝ったのかが不明で、具体的な状況が想像できません。
改善後:「12時00分、利用者様と一緒に台所へ移動。献立を確認し、味噌汁の温めとご飯の盛り付けを利用者様が行い、私は配膳と後片付けを行った。食事中、むせる様子はなく、完食された。」
→ 準備の段階から食事の状況、後片付けまで具体的に記録されており、サポートの内容が明確に伝わります。
介護記録での使用を避けたい言葉
介護記録には、利用者さんを侮辱したり、見下したりするような不適切な表現は絶対に使用してはいけません。
「しつこく何度も聞いてきた」「勝手に入ってきた」「ボーっとして」などの利用者を侮辱・見下す表現は使いません。
改善前:「何度も同じことを聞いてきて、困った。」
→ 利用者さんの行動に対する否定的な感情が表れており、客観的な記録とはいえません。
改善後:「〇〇について、先ほどもお伝えしましたが、再度確認される場面がありました。ゆっくりと、分かりやすい言葉で再度説明を行いました。」
→ 利用者さんの行動を客観的に描写し、それに対する自身の対応を記録しています。
難しい表現や専門用語
介護の現場では、専門的な用語が使われることもありますが、記録を読むのは介護の専門家だけではありません。ご家族など、介護の知識がない人にも分かりやすい言葉を選ぶように心がけましょう。
・「褥瘡」じょくそう=寝たきりなどで体重で圧迫され皮膚が赤くなったり、ただれたりすること。床ずれ。
・「傾眠」けいみん=ウトウトして、声掛けなど軽い刺激で意識を取り戻す程度の軽度の意識障害の一つ
改善前:「清拭時、褥瘡の状態を確認。」
→ 「褥瘡」という専門用語は、一般の方には理解しにくい場合があります。
改善後:「清拭の際、背中とお尻の皮膚の状態を確認。赤くなっている部分や、傷のようなものは見当たりませんでした。」
→ 専門用語を使わずに、具体的な皮膚の状態を分かりやすく記述しています。
記録漏れ
記録すべき内容を忘れてしまうことを防ぐためには、訪問後できるだけ早く記録を作成する習慣をつけましょう。特に、金銭のやり取りがあった場合は、金額や内訳を正確に記録することが重要です。
対策: 訪問中に簡単なメモを取る、記録する項目を事前にリスト化しておく、などが有効です。
主観的な表現
観察した事実に基づいて記録することが原則です。自分の感情や解釈を加えた主観的な表現は避けましょう。
改善前:「今日は疲れているように見えた。」
→ あなたの主観的な判断であり、具体的な根拠が示されていません。
改善後:「朝から、普段よりも言葉数が少なく、座っている時間が長かった。午前中のレクリエーションへの参加も控えられた。」
→ 具体的な行動や様子を記録することで、客観的な状況が伝わります。
訪問介護記録を効率よく作成するためのヒント
5W1Hを意識する
訪問介護記録を作成する際に、5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を意識して記述すると、情報が整理され、分かりやすい記録になります。特に、利用者さんの状態変化や、特別な対応を行った場合には、これらの要素を明確にすることが重要です。
例えば、利用者さんの状態変化では、この5W1Hが発揮できます。気分が悪くなったのはいつからなのか、何をしていた時そうなったのか等、聴き取ることが重要ですね。
テンプレートを活用する
記録の形式を統一することで、記載漏れを防ぎ、効率的に記録を作成することができます。以下のような項目を含むテンプレートを作成しておくと便利です。
テンプレート例:
- 日付・時間: 〇年〇月〇日(〇)〇時〇分~〇時〇分
- サービス内容: (例:排泄介助、居室清掃、買い物同行)
- 利用者の様子: (例:穏やかな表情、食欲不振の訴えあり)
- 特記事項: (例:〇〇様より、△△について相談あり。〇〇(家族名)に電話連絡し、状況を報告。)
- 申し送り事項: (例:明日は〇〇の予定。〇〇に注意が必要。)
訪問直後に記録を作成する
サービス提供の内容や利用者さんの様子は、時間が経つにつれて記憶が薄れてしまいます。可能な限り、訪問直後に記録を作成することで、正確な情報を記録することができます。訪問中に簡単なメモを取っておくのも有効な手段です。
記録作成に役立つツールやアプリ
近年では、紙媒体の記録に代わり、電子記録システムや介護記録アプリを活用する事業所も増えています。これらのツールは、情報共有の迅速化、記録の標準化、入力の手間軽減など、多くのメリットがあります。
- 電子記録システムの活用:
メリットとして、情報共有が容易になり、誤記防止や時間短縮が期待できます。 - おすすめアプリの例:
(お住まいの地域や利用しているサービスに合わせて具体的なアプリ名を記載してください)これらのツールを活用することで、記録業務の効率化を図り、より利用者さんに向き合う時間を増やすことができるでしょう。

まとめ:質の高い記録は、質の高いケアに繋がります
訪問介護の記録は、利用者さんの安全を守り、より質の高いサービスを提供するために不可欠な業務です。具体的かつ簡潔な記述を心がけ、客観的な事実に基づいて正確に記録を残しましょう。そして、テンプレートや便利なツールを積極的に活用することで、記録業務の効率化を図り、日々の業務負担を軽減してください。
これからも、頑張るヘルパーさんを心から応援しています!
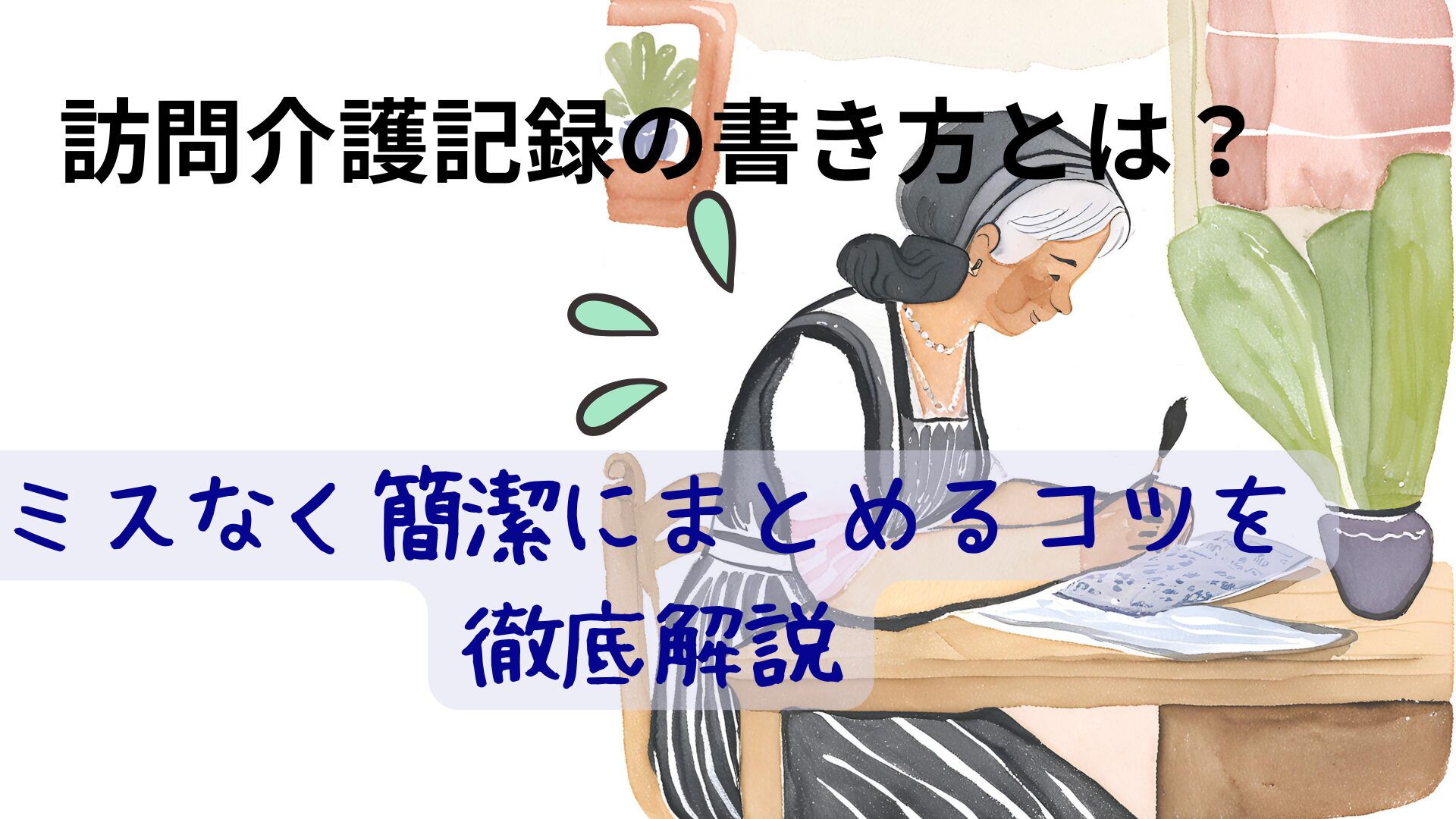
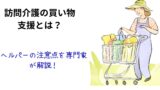
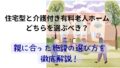
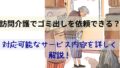
コメント